
―社会理論と経験的社会研究
タルコット・パーソンズ後 50 年
あるいは、ある大学教員人生
19.社会調査実習
助手時代を含め教員生活41年、そのうち23年、最も時間を投入したのは、第一文学部配当の「社会調査実習」であったかもしれない。これは、90分授業と言いながら、半日どころか、毎日、調査実習室にいなければならない、まさに実習であった。
1987年度、1989年度、1990年度は、池子米軍家族住宅建設反対運動を調査対象とした。1988年度は、テレビ・コマーシャルの言説分析を試みた。そこで思ったことは、映像よりも、学生は外のフィールドに出たほうがよいであった。

1991年度は、統一地方選挙を主題に、区長選挙、区議会議院選挙への投票行動と意識をめぐって練馬区を集中的に調査した。ポスト冷戦時代となり、自由民主党が、党中央と、東京都連とで分裂して異なる候補をそれぞれ立てた選挙であった。
そしてこの年度は、たいへん精力的な報告書をまとめ、仲のよいクラスであった。ということもあり、それまでの調査実習メンバーたちが集まって懇親会を開いた。

1994年は、「責任ある変革」を掲げて登場した細川護煕内閣を主題にした。この間、在外研究で1992年後期、93年前期と、結果2年あいたことと、バブル崩壊後の不景気が就職状況に影響して、学生たちに変化があり、私としっくり行かない年度であったように思う。
思ったのは、細川の日本新党について、あるいは日本の政治の変化について、さほど関心がないのではとさえ感じた。
学生担当教務主任、早稲田祭教職員側委員、教育の国際化検討委員などに時間を割かれ、しばらく時間があいて、1998年度は、心機一転、青島都知事誕生、世界都市博覧会中止を題材に、港区台場で、これまでに倣って調査票郵送、学生調査員が訪問回収する方法で実施した。

しかし時代が変わったことを強く感じた。とりわけ高層住宅は、オートロック、表札がないのが普通となり、訪問調査は難航し出した。そして学生の意識の変化だろうか、フィールドをつねに回っていた私は、回収中のある学生に出会った。ねぎらおうと思ったら、連れの女性がいて、「どなた」と聞いたら、「彼女です」と無邪気な反応。調査実習も、彼女同伴かと驚いた。 この年度が、調査員派遣訪問回収の最終年度となった。
1999年度は、この年に行われた東京都知事選挙で石原慎太郎が当選したこともあり、その投票行動と意識を主題に、郵送調査を、東京都内8地区(練馬、杉並、港、新宿、国立、江戸川、大田、多摩)、各選挙管理委員会で投票者名簿からサンプリングして、6400サンプルを抽出、2300サンプルを回収した。この種の大規模郵送調査を、社会調査実習の軸にしていけばよいと思った。しかしながら、これは莫大な郵送費用がかかることが深刻な問題であった。

2000年度は、予算が枯渇したこともあり、また前年度に膨大なデータを収集したので、これの分析と報告書をまとめることを主題に調査実習を行った。これも、SPSSはじめソフトウェアの利用習得とともに、社会統計学の基礎知識を実際に学ぶということでは意味ある実習となった。
2001年度は、これを受けて、データをCDとして公開提供されるようになった国勢調査データを利用した調査実習とした。


フィールドに出ない郵送調査、そしてコンピュータに向かっての分析、報告書も電子媒体となり、社会調査実習が大いに変化せざるをえなくなったと実感した。
社会学の調査実習室であった126教室もそこに至る過程でコンピュータ・ルームに改造していくことになった。その設計は、そもそも私が行なったものであった。
再び在外研究で、2年あいて、2004年度は、やはり2001年の東京都知事選挙の投票行動と意識を主題にした。
しかしながら、いよいよ個人情報保護の時代となり、選挙人名簿の目的外利用は不可能となり、これまで行なってきたサンプリングが不可能となった。代替した方策は、ゼンリンの『住宅地図』を用いてサンプリングするという方法である。これにより、東京都内7地区(杉並、港、新宿、国立、江戸川、大田、多摩)から6300サンプルを抽出し郵送調査を実施した。
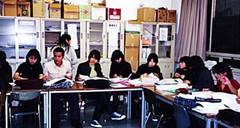
回収状況は、杉並23.4%、港17.2%、新宿20.0%、国立23.3%、江戸川16.1%、大田19.8%、多摩19.6%となり、面白い地域差が出た。
さらに2005年度は、同様の方法で都内4地区(品川、豊島、葛飾、立川)から4800サンプルを抽出し、22%の回収率を得た。基本主題は、東京都知事選挙での投票行動と、とりわけ石原慎太郎都知事についての意識であった。
これらは、まさしく拙著『石原慎太郎の社会現象学』へとつながる基本データの収集であった。だが、社会調査を実施する環境が、対象者選定の困難とともに、政治状況への学生の問題意識の減退を大いに感じるようになったことも事実だった。
2007年度から、文化構想学部、文学部の開設で、長く続いた第一文学部社会学専修の調査実習は終わることになり、私も文化構想学部社会構築論系に移ることとなった。そして、私の経験的社会研究も、社会調査実習によるデータ収集から、マクロミルのようなネット調査を専門とする企業に委託した調査となっていった。
これは、手間がかからないのであるが、調査票を議論しながら作り、また回収する際に見える社会、人という発見はわからなくなっていき、とりわけ若い学生にとって、調査がデータ分析のみの世界へとなっていき、フィールドとの関係が大いに変わった。
文化構想学部社会構築論系に移り、「共通演習」と称して、2008年から19年までは、私がネット調査会社に委託した調査データ、あるいは私がこれまで行なってきたインタビュー・プロトコール、自由回答を分析する演習と、社会統計学の基礎を学ぶ演習を進めて行った。
前者は、さらに2019年から22年まで、Google Formを用いてアンケート調査を行ない、データをSPSSで使えるように加工し、今風の社会調査実習を実施した。
これは意味があると思ったが、受講生の、とりわけコンピューター・スキルに能力差がありすぎ、なかなか焦点を定めにくい問題が浮かんだ。
学年進行のカリキュラムを崩した弊害である。学生が、自由に「好きな」科目を履修することを優先したために、能力的に、自分がどの位置にいるのかがわからなくなってしまうという、大学での学び方に改良せねばならない深刻な問題が生じていると思った。
高級なスマホ、i-bookを持って授業に出ているが、WordとPower Pointあるいはブラウザーしか使うことができない学生が少なくない。
第二外国語を捨て、コンピューター・スキルもないという深刻な問題が、文化構想学部、文学部のカリキュラムには存在していると思う。これは、教員側の責任でもある。どんな仕事をする場合にも必要なスキルを身につける機会を大学は提供しなければならない。
社会調査に必要な費用は、2年生のときに社会学専修に進級し、卒業までに3年間、半期5000円、合計ひとり3万円、22人の実習生であれば、66万円が最大の予算であったが、実習期間中、合宿費用に使用すると、ほとんど調査には使うための費用捻出ができなくなった。
理工学部教員などは、合宿は、学生自弁が当然だと言い、また金額では数倍の実験実習費を授業料と併せて集金しているが、私は、こういう金持ち当たり前主義の発想には終始反対であった。
社会調査は、調査者と、チームの力が絶対であり、たんなる実験、調査そのものだけで成り立つはずはないし、理工学部のように支援職員が配置されているわけでもない。
裕福な家庭の学生ばかりではないことを知れば、合宿さえも、大変な費用負担に感じる学生もいる。社会調査で現地に泊まり込むこと。あるいは調査票回収にかかる交通費も必要なものであった。
その上で、調査票印刷費、郵送費用、録音テープなどの費用、報告書印刷、郵送費用など、その工面はたいへんなことでもあった。
早稲田大学の教員であるので、在野精神の実践をせねばならず、官有物払下げ事件を思い出さねばならないわけではないが、税金が原資である官の研究費は、基本的に頼ることはしない方針であったが、社会調査実習の調査規模を充実させるためだけに申請、使用することはした。
1987年度科学研究費補助金奨励研究80万円、1994-5年度科学研究費補助金 基礎研究(C) 160万円は、池子米軍住宅建設反対運動調査。1998-9年度同基礎研究(C)110万円、2004-5年度基礎研究(C)310万円は、東京都知事選挙投票行動調査のために申請し、調査実習費ではまったく足りない調査票郵送費などの費用とした。6000通になると郵送費だけで100万円を超える。
2009-10年度同基礎研究(C)370万円は、やはり東京都知事選挙投票行動調査、これは調査会社外注で、パネル調査として繰り返し、社会構築共通演習でデータを使用した。
目次に戻る
次へ
Copyright 2024 Prof.Dr.Mototaka MORI