
―社会理論と経験的社会研究
タルコット・パーソンズ後 50 年
あるいは、ある大学教員人生
20.演習とゼミ
「社会調査実習」という実習科目は、たいへん特異であった。第一、第二文学部ともに、当然のことであるが、講義科目とともに、演習科目があった。
「実習」とは異なり、古典的には文献講読、資料読解と議論により成り立つと考えてよいが、既述のとおり、そこで村上泰亮『新中間大衆の時代』、村上泰亮・公文俊平・佐藤誠三郎『文明としてのイエ社会』(中央公論社)、上野千鶴子『主婦論争を読む』から、広くマルクス『経済学・哲学草稿』『ドイツ・イデオロギー』、ヴェーバー『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』『社会科学および社会政策の認識の客観性』、デュルケム『自殺論』『社会学の方法的規準』など有名著作について扱う演習も担当してきたし、ドイツ語原書講読では、Habermas, Glauben und Wissenも読んだ。
1996年第二文学部のカリキュラム改革により、それまでの社会専修では主要には、上述の社会科学者を中心に精密講読をしてきたが、思想・宗教系専修に移ってからは、カッシーラー『シンボル形式の哲学』、フッサール『デカルト的省察』の精読も、少人数のたいへん充実した演習で読み通すことができた。

まさに、早稲田大学に来る学生には、そういう能力を備えた人が少なからずいるということであった。それぞれに優れた学生たちと遭遇することができたことは、私にとってかけがえのない宝となった。
第一文学部、第二文学部ともに通年、あるいはセメスター単位の科目として、講義、演習、さらに実習を配置してきた。
私は、これがベストだと思ってきたが、政治経済学部、法学部、商学部、あるいは歴史的には慶應義塾大学経済学部が行なってきた2年制の「ゼミ」制度を設置することが、新たにできる文化構想学部の特徴だとされた。私は、これに終始、そして今も反対である。同じ教員と2年間もつながっていることは、百害あって一利なしだと思う。
若い知性は、さまざまな人と出会う必要があるし、カリキュラムは、チームで成り立つものでなければならない。余人をもって代え難しと選ばれた専任教員が、在外研究、国内研究で、ゼミゆえに、自分に代わる非常勤講師に容易に任せる無責任よりも、専任がチームでカバーできることが必要であり、専門性よりも属人性が強いゼミ制度には批判的にならざるをえない。
しかし日本的「ゼミ」待望の雰囲気は教授会決定となり文化構想学部開設、その初年度学生が3年となる、2009年度から「ゼミ」なるものが始まることとなった。
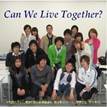
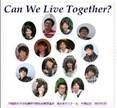
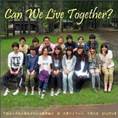
2年間4セメスターあり、第1セメスターは、社会科学の基本概念の習得と確認、第2セメスターは、それをもとに現在まさに問題となっている社会事象について分析報告をする。第3セメスターは、次年度生の第1セメスターに討議者となること、第4セメスターは、卒業論文(ゼミ論文)を仕上げるという内容で、2年制ゼミを編成していった。


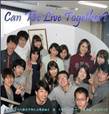
日本社会学会で言う、いわゆる「社会学」から離れ、文学部社会学コースとも切れ、文化構想学部社会構築論系という、新しい世界での展開であり、そのこともあり、2015年度から、拙著『理論社会学 ―社会構築のための論理と媒体』を第1セメスターの教科書として用いることにした。
ゼミは、2009年度から2025年度まで続けた。もちろん、早稲田大学にやってくる、そして私の「ゼミ」を選択してくれる学生たちは選りすぐりであり、第一、第二文学部のときには経験しなかったが、2016年度には卒業論文により「小野梓記念学術賞」を受けた学生もいる。
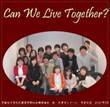


私が心がけたことは、日本の大学の「ゼミ」という悪しき時空。まさに山崎豊子や花登筺による船場の商家もののような徒弟世界、「弟子」を作ること、「先輩―後輩」を作ること、あるいは気の合う仲間だけ選抜した学生同好会、あたかも士官学校、兵学校のように「○○ゼミ第○期」などという年次序列のある勘違いした、さまざまな時代錯誤だけは、絶対にするまいということであった。
私が教えることは、社会科学の方法であり、素材は学生が自由に創意工夫で選ぶということを徹底したつもりである。
上述の小野梓記念学術賞受賞作品も、私がかかわってきた研究素材とは異なるオリジナルなものであった。「ゼミ」を進めるのであれば、教員とはまったく違う学生たちの、どこかにありうる特徴を延ばすこと、これに寄与することに注力したつもりである。


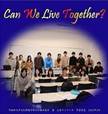
それと併せて、敢えて付け加えれば、同年、あるいは前後3年の人間関係が生まれ、それが時を超えて、私にとって、かつての子安先生のドイツ語クラスや、丹下先生の社会学研究や社会学演習のようであれば、あるいはかつての演習や実習における人間関係が生まれれば素晴らしいということであった。
さて、文化構想学部ゼミ16年をふり返ると、2018年度以前と、それ以後、学生の雰囲気が変化したと感じている。あるいは、私が歳を取ったゆえかもしれない。
2007年度に入学し、2009年度から「ゼミ」に参加した学生たちは、「文化構想学部」という、それまでどこにもなかった名称の学部であり、何もないところからの始まりであった。
実際、文学部が第一文学部の施設を継承したため、例えば社会学実習室のようなものも、専用のコンピュータ・ルームもないところから始まったこともあり、また戸山キャンパス建て替えで、始まりはプレハブ教室であり、私のゼミは、本部8号館のゼミ室を使用させてもらっていた。
学生のことを思い、施設の融通をしてくれてもよいものだと思ったが、なんとも頑なであった。
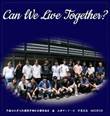


そういう劣後環境ゆえにか、学生自身が、たいへん主体的に動いたと感じるし、社会構築論系全体で学生の交流を作っていくための「社構会」の運営も、森ゼミの優れた学生たちが、リードして進めてくれた。


これに変化があったとしたら、「文化構想学部」というものが、ブランドとなったということなのだろう。いわゆる偏差値においても高く位置づけられ、ある種の安堵が生まれたということかもしれないし、経済状況が、アベノミクス以後、表面的に好転し、就職状況が活性化したということもあると思う。
2011年3月、東日本大震災により、文化構想学部最初の卒業生たちの式も中止となったし、それからしばらく、あらゆる点で厳しかったと思う。「就活」でまわる企業数も桁違いの多さであったが、経済状況の変化とともに、学生の意識も大いに変わっていったように思う。
特徴とされた「ゼミ」も、講義科目、演習科目とならぶ、ひとつの科目でしかなくなっていったのであろう。言い換えれば、単位取得が得られればという時代となり、これを学びたいゆえに、このゼミというよりも、「人気だから」「みんなが選ぶから」という類いの選択が行われているように感じたこともあった。
その原因は、体系的なカリキュラムで学ぶという前提が崩れてしまっているからであろう。「大学へ入ったら、好きな科目を好きなように取れる」と、高等学校までの受験オンリーの詰め込み暗記世界からの誤った解放のように思う。
かつての社会調査実習のように、社会経験が圧倒的にある大人たちと接する緊張感、あるいは図書館に籠もって文献資料をわかるまで渉猟するが学問であるという時代とは違う現在となり、机には、つねにノートパソコン、タブレットがあり、検索すれば瞬時に答えがわかり、ときには報告も、スマホにあるメモで可能な時代となった。
教室という時空自体が、Zoomの利用進展とともに、大いに変化している時代、昭和10年代に生み出されたニッポンの「ゼミ」。この発想は、その時代、大学進学率10パーセントに満たない時代、大学に行くことができた裕福な青年たちが、特定の学校を通じてだけ、就職に、研究者養成に、有利なコネクションを享受できるための場として考案された慣行と私は理解している。
そうした歴史的に特異な慣行が、今も、機能していて妥当なのかということは、是非、問うてもらいたいと思っている。
目次に戻る
次へ
Copyright 2024 Prof.Dr.Mototaka MORI