
―社会理論と経験的社会研究
タルコット・パーソンズ後 50 年
あるいは、ある大学教員人生
13.長期信用銀行制度と貨幣発行自由化論
バブル崩壊、それは日本の経済システム、戦後、いや明治以来の村上泰亮いう「追いつき型」近代化、すなわち経済システムと社会との関係を根本的に変えることができるかという問いであった。
そもそもの関心「経済理論の社会学による基礎づけ」、言い換えれば経済に社会はどう関係しているかという問題を、この問題に援用することが、新たなテーマとなった。
『アルフレート・シュッツのウィーン』で、ミーゼスについては大いに論じたが、ミーゼスのプライベイト・ゼミナールに、シュッツとともに参加していた人たちのひとり、のちに20世紀、最重要の経済学者ハイエクについての研究は不十分であった。
それへの追加研究が、『フリードリッヒ・フォン・ハイエクのウィーン ―ネオ・リベラリズムの構想と展開』(新評論 2006年)であるが、ハイエクが戦間期のヨーロッパ経済を細かく捉えていたのに倣い、日本の「追いつき型近代化」を可能にした経済制度の特質である長期信用銀行制度、その興亡に着目した。実際、バブル崩壊後、長期信用銀行制度も崩壊する。

直接金融である証券投資を後ろに退け、限られた階層にのみ許容し、銀行による間接金融を軸にするも、銀行に制度的階層を設けて、日本興業銀行、日本勧業銀行など、金融化していった寄生地主のファイナンスと、庶民の郵便貯金という特異な配置関係を設定して、貨幣と貨幣派生体との循環システムを構築して財政運営をしていく日本の財政構造について社会理論的アプローチで辿っていった。
これと並行して、ハイエクがその晩年、一般には無視をされたに等しい貨幣発行自由化論に着目した。
それが、『貨幣の社会学 ―経済社会学への招待』(東信堂 2007年)であり、もともとは第一文学部社会学専修での「社会学研究」で取り上げていた問題であり、文化構想学部発足後は「社会理論」として講じることになった。この問題には興味関心を持ってくれる優れた学生が少なくなく、その方面で大学教員、ジャーナリストとして活躍している頼もしい方々もおられる。

貨幣発行自由化論は、ハイエクが提唱した1970年代には、来るべき欧州統一通貨に対して、すなわちそれがグローバルのように感じられるかもしれぬが、統一欧州という大きな国家が発行する通貨にほかならない。それよりも、貨幣そのものの脱ネーション化が必須であるという主張であった。
しかし、この革命的な発想が理解されるようになるのは、2009年になって、仮想通貨、すなわちサトシ・ナカモトによるビットコインの構想と実践であった。私は、これの可能性、そしてそれを理論的に予言したハイエクについて、大いに感心をした。実際、きわめて多数の仮想通貨が出現し、まさに貨幣そのものの自由化、貨幣そのものが商品化するという意味での貨幣商品説の実現であった。
『未来社会学 序説 ―勤労と統治を超える』(東信堂 2018)は、そういう未来社会において、かつ超高齢化が進行していく日本において、何が必要かということを問おうとしたものであった。しかしながら、これを2018年度、社会構築演習で教科書としたが、なかなか学生が十分に理解しているようには思えなかった。
『貨幣の社会学』についての興味関心と、どうして違うのかがわからなかった。学生たちのパースペクティブは、「ジャパンアズナンバーワン」への郷愁、年寄り同様に、やはり過去に向いているのか、あるいは、私自身が年齢を重ね、若い人たちと関心がずれてしまったのかという疑念を抱いてしまうほどであった。
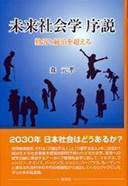
今ひとつ、Facebook(現meta)が、LIBRAという新しい仮想通貨を構想し、日本の銀行においても、類似の構想がされたのだが、興味深いことに、各国政府、中央銀行は、多数生まれた仮想通貨にも、構造が本質的に異なるがLIBRAについても、きわめて制約的行動を加えるようになり、仮想通貨は、「暗号資産」として、貨幣ではないという位置づけがなされるようになっていった。
これは、ハイエクが構想した貨幣の脱ネーション化は、再びネーション化の徹底に虐げられる結果になったということである。
目次に戻る
次へ
Copyright 2024 Prof.Dr.Mototaka MORI