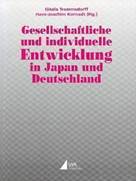

―社会理論と経験的社会研究
タルコット・パーソンズ後 50 年
あるいは、ある大学教員人生
11.ドイツ日本社会科学会
そうした仕事にひと区切りがついた、1998年9月、第5回ドイツ・日本社会科学会(German-Japanese Society for Social Sciences)大会を早稲田大学国際会議場で私が世話人として開催することができた。
この学会は、1994年第3回大会が関西大学で開催され、この学会の副会長をされていた富永健一先生に誘われて入会し報告することになった。
「Basisdemokratie und Lokale Politik (草の根民主主義と地方政治)」という池子米軍家族住宅建設反対運動の研究成果を報告し、これは好評を得た。その結果もあり、教育心理学の並木博先生(早稲田大学教授)とともに、続く1996年のコンスタンツ大学での開催の次、1998年、第5回大会を早稲田大学で開催することになった。
その後、2004年ヒルデスハイム大学、2006年金沢大学、2008年オスナブリュック大学、2010年法政大学、2013年バート・ホンブルク、ヴェルナー・ライナー財団、2015年ドイツ日本研究所東京、2018年オスナブリュック大学、2019年ハンブルク大学、2022年上智大学、2024年ドイツ日本研究所東京での第17回大会まで、長い間にわたってお世話になった。たいへん光栄で有り難いことである。
会長のハンス・ヨアヒム・コルナット先生(ザールブリュッケン大学教授、ドイツ心理学会会長)、副会長のギーゼラ・トロムスドルフ先生(コンスタンツ大学教授)にはたくさんのことを教えていただいたが、私のそもそもの出発、目標とした富永健一先生とも、またドイツ社会学研究会、ルーマン研究でも多くのことを教えられた徳安彰先生とも長い関係が続いていった。
富永先生が2008年に出版された『思想としての社会学 ―産業主義から社会システム理論まで』(新曜社)という社会理論、社会思想の大著をめぐって、2009年立教大学で開催された第82回日本社会学会大会シンポジウムで討議が催され、批判者として登壇させていただいた。
そうした場を与えていただいたことは嬉しかったし、駆け出し以来、目標にしてきた偉大な先生に物申すことができたことは、たいへん光栄なことであった。
2010年『思想』(岩波書店 4月号)「思想の言葉」で、富永先生はそのときのことを記され、私の意見に、たいへんご不快であったとあるが、その後も、ドイツ日本社会科学会をつうじてお話をすることが続いていった。
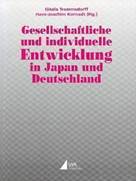

必ずしも、この学会のためというわけではなかったが、1994年の報告以来、日本の民主政治について、この学会で報告をすることが通例のようになっていった。
目次に戻る
次へ
Copyright 2024 Prof.Dr.Mototaka MORI