
―社会理論と経験的社会研究
タルコット・パーソンズ後 50 年
あるいは、ある大学教員人生
10.『アルフレート・シュッツのウィーン』
さて、1987年専任講師にしていただき、5年を経た1992年、在外研究の機会を与えていただき、1980年に行うことのできなかったことを、改めてウィーンで徹底的に行う機会をいただいた。
1990年、『社会科学討究』(早稲田大学社会科学研究所 第37号(3))に「アルフレート・シュッツとウィーン ―社会的世界の構成現象学成立事情研究序説」という論稿を掲載していただいた。
その主旨は、シュッツは、主観主義の社会学として、下田先生はじめ、多くの「現象学的社会学」を掲げる同年代、年長世代たちによるシュッツをめぐる解釈に、大いなる疑問があったからである。
シュッツが学んできたプロセスを追っていくと、また主著『社会的世界の意味構成』を精読していくと、主観主義社会学の構築などよりも、一方で、ルートヴィヒ・フォン・ミーゼスの限界効用学派、ハンス・ケルゼンの純粋法学、あるいは批判対象としてのオトマール・シュパンの復古主義が重要なテーマとして展開されている。
これはまさに経済学、法学など他の社会諸科学と、社会学の関係、とりわけその使命が取り上げられているということであり、現象学も、その問題系は、素朴に主観主義を主張しているのではなく、主観、客観の存立前提を問うということである。
他方で、音楽、演劇などへの関心は、ただ主観的感覚の開陳などではなく、きわめて理論的な内容であるということを理解したからである。
素朴に、主観主義として、パーソンズを客観主義、さらにはパーソンズは保守主義、シュッツは革新的という、つまらない対置を超える研究が必要だと思ったところが大きい。
1992年から3年にかけて、ウィーン大学哲学科のアルフレート・プファービガン先生に多々教えられ、ウィーン大学図書館、オーストリア国立公文書館、ウィーン市役所資料室、オーストリア商事裁判所資料室に通った。
さらにドイツ、コンスタンツ大学に開室されたばかりの「アルフレート・シュッツ文庫」にイリヤ・スルバール先生を尋ねて、手書きの遺構、草稿、手紙などを多々読ませていただき、たくさんのノートを取ることができた。これは、そう簡単にできるものではないだろうと思っている。
重要な遺構と草稿は、『アルフレート・シュッツ全集』(Alfred Schütz Werkausgabe, Herbert von Halem Verlag)として2023年全巻が公刊されているが、その長大な作業が始まる前にそれに関わる人たちと会うことができ、知的好奇心に満ちた楽しい経験であった。
かつて12年前に遊学させていただいた8区にある、ランゲガッセに住まいを借りた。つれあいは、ウィーン大学で聴講しつつドイツ語を磨き、私は図書館、文書室の日々であった。
家主であるライニンガー夫妻は、写真家であり、美術館の絵画分析など、またしばしば料理講習をしていただき、たくさんのことを教えていただいた。それがきっかけで、8区のフォルクスホッホ・シューレのウィーン料理教室にも、つれあいと通った。実にさまざまな経験をすることができた。
私自身の研究成果は、拙著『アルフレート・シュッツのウィーン ―社会科学の自由主義的転換の構想とその時代』としてまとめた。
シュッツの、そもそもの理論構築のレリバンスを、1920年代ウィーンの社会科学、政治社会、経済状況、芸術と重ね合わせて、公開されている文献のみならず、未公開の草稿、書簡にまで遡求した研究成果であり、これを超えるものは、未だ知らない。
量的にも、78万字以上あり、1994年9月、早稲田大学文学研究科に博士号請求論文として提出することができ、翌1995年12月、当時の奥島孝康総長から学位記を授けられた。

同年9月には、新評論から748頁になる書として出版していただくことができた。社会学のみならず、経済学者、哲学者、倫理学者からも、少なからず書評、引用をいただくこととなり、有り難く幸せなことであった。
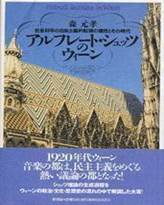
『アルフレート・シュッツのウィーン』を出版した1995年9月、ほぼ同時期、弘文堂から社会学についての教科書『モダンを問う ―社会学の批判的系譜と手法』を出版させていただいた。
これは、とりわけ講義「社会学」、講義「社会学研究」、そして社会調査実習での成果を織り交ぜた内容豊かなものであった。翌1996年には『逗子の市民運動』も御茶の水書房から出版することができ、私の教員生活、その一区切りということであったのかもしれない。


実際、そうであり、1994年夏から翌年秋まで早稲田大学教員組合書記次長、1996年9月から98年9月まで第一文学部学生担当教務主任に就き、これまでにない仕事をすることになった。
目次に戻る
次へ
Copyright 2024 Prof.Dr.Mototaka MORI