
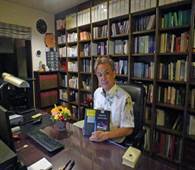
―社会理論と経験的社会研究
タルコット・パーソンズ後 50 年
あるいは、ある大学教員人生
27.最後にあらためて
たいへん長い期間にわたって、第一文学部社会学教室、第二文学部社会専修教室、同・思想・宗教系専修教室、文学研究科社会学専攻、文化構想学部社会構築論系教室の諸先生、助手諸氏、さらには文学学術院教授会の諸先生方から、多くのことを教えられ、多くの議論をすることができたことは、恵まれて幸せなことでありました。心より感謝を申し上げます。
通常の教員業務のみならず、学生担当教務主任、教務担当教務主任、早稲田祭教職員側委員、教育の国際化検討委員、大学年金委員、教員組合、健康保険組合など少なくない役務をつうじても、たくさんの職員の方々に多大なご助力をいただきお世話になりました。有難うございます。
在職期間中、合計3399頁11冊の著書を刊行することができました。それには、出版社、ならびに優しく、ときに厳しい編集者の方々に多大な助力をいただくことができ、それは御礼しきれぬほど有り難いことでありました。
助手をさせていただいていた時代、共訳書ハーバマス『意識論から言語論へ ―社会学の言語論的基礎に関する講義(1970/1971)』の刊行を引き受けてくださった、マルジュ社の桜井俊紀社長、『アルフレート・シュッツのウィーン』『フリードリヒ・フォン・ハイエクのウィーン』では、新評論の二瓶一郎さん、武市一幸さん、最初の教科書『モダンを問う ―社会学の批判的系譜と手法』(1995年)では、弘文堂の中村憲生さん、池子米軍住宅建設反対運動研究のモノグラフは、御茶の水書房の橋本盛作さんにお世話になり、心から感謝申し上げます。
そして「世界の社会学・日本の社会学」というシリーズで企画された中の一冊『アルフレッド・シュッツ ―主観的時間と社会的空間』(2000年)以来、多くの拙著を刊行してくださった、東信堂の下田勝司社長には、永年にわたり、たくさんのことを教えていただき、心より感謝を申し上げなければならないです。本当に有難うございました。
しかし、何よりも感謝せねばならないのは、繰り返しになりますが私の授業で真剣に取り組んでくださった多数の学生諸氏であり、その機会を与えてくれた早稲田大学でしょう。有難うございました。
長い間にわたって、身勝手きわまりない私と、東京練馬三原台、高野台、ウィーン、逗子、そしてまたウィーン、逗子へと、いろいろなところへ連れ合ってきてくれたパートナーにも心より御礼を申し上げたい。あなたなしには、ささやかな仕事もなしえなかったでしょう。有難うございます。
そして、逗子拙宅の書斎で、いつも私の仕事の傍らで見守ってくれていた相棒にも感謝している。

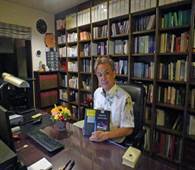
目次に戻る
次へ
Copyright 2024 Prof.Dr.Mototaka MORI